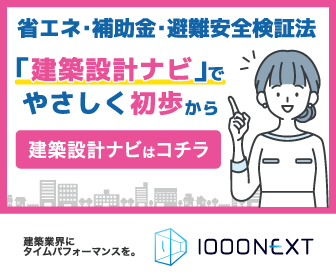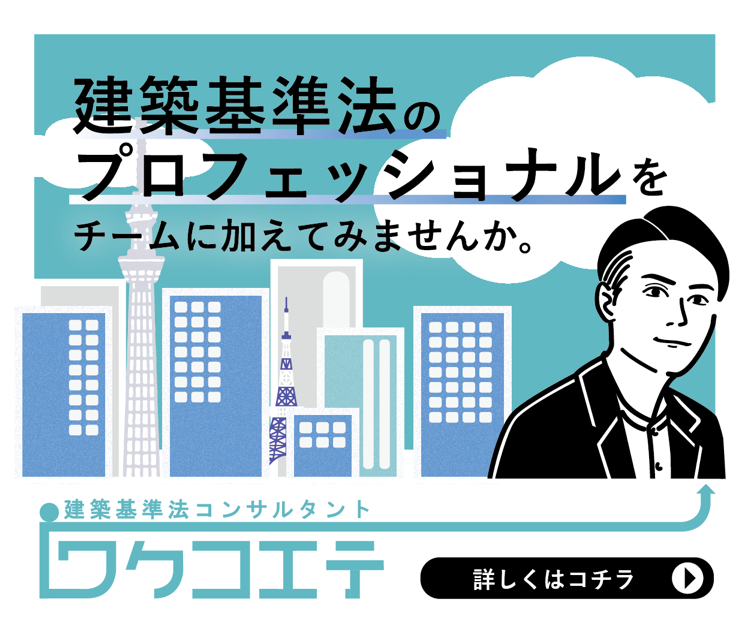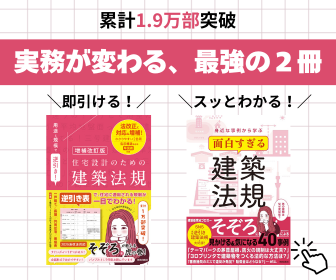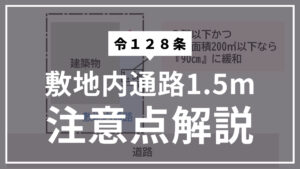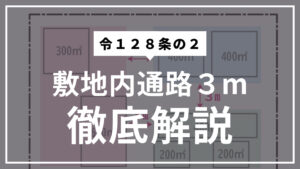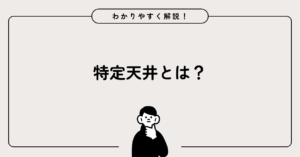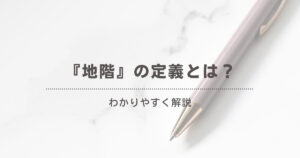PR
【2026年最新法令】三号建築物とは?確認申請や検査時の特別扱いについて解説
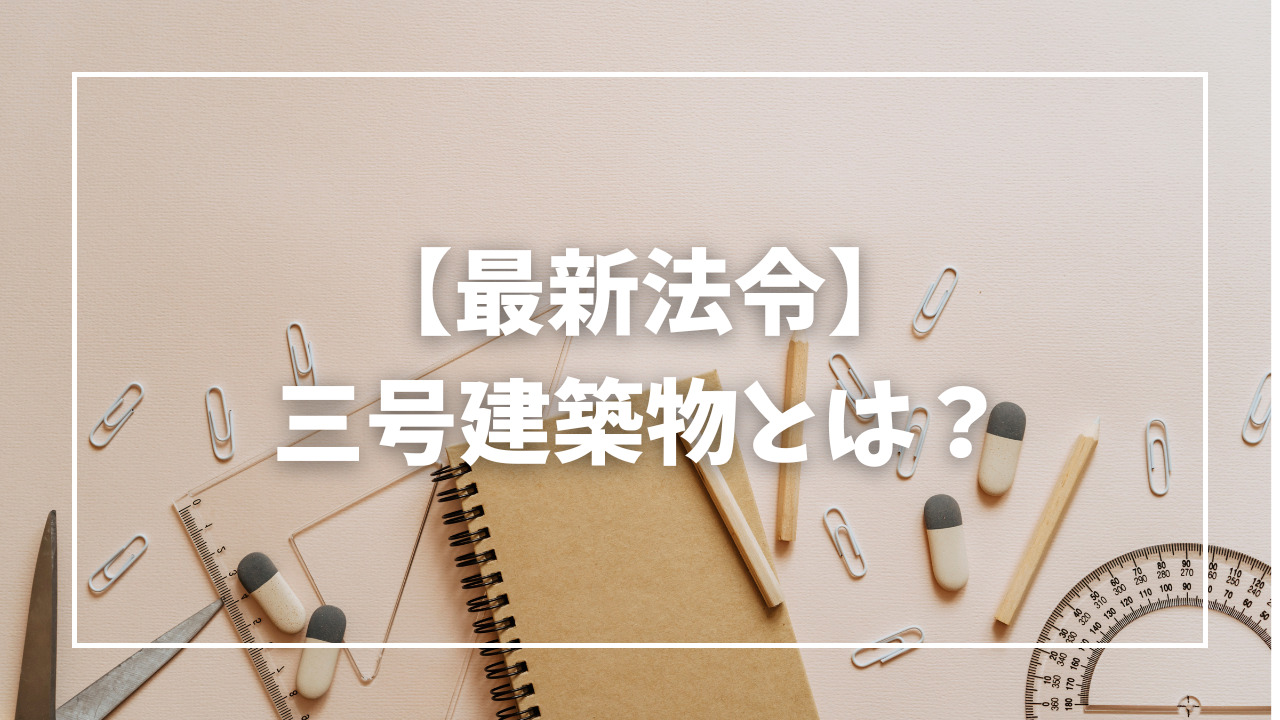
本記事の解説内容: 令和7年(2025年)11月施行の最新改正に対応した内容です。

三号建築物ってどんな建築物?
三号建築物は、建築基準法上の位置付けは?
こんなお悩みに、答えます!
まずは結論から…
✔︎三号建築物とは、建築基準法6条1項三号に定義される小規模建築物
✔︎三号建築物の建築基準法上の位置付けは、手続き関連が簡略化される建築物(ただし、手続き関連の規定が緩いだけで、他に違いはなし)

三号建築物は、令和7年4月1日に法改正されました!
今回は、法改正の内容を踏まえ、わかりやすく解説していきます!(X:sozooro)
 そぞろ |
元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |
三号建築物とはどんな建築物?
三号建築物とは、平屋で200㎡以下の建築物のこと(構造は問わない)

ざっくり言うと、数多くの建築物の中でも、比較的小規模な建築物が三号建築物です!
三号建築物と呼ばれる理由は単純で、建築基準法6条1項『三号』に定義されているからです。
念の為、名称の根拠となる建築基準法6条1項を確認してみましょう。
建築基準法6条1項
(本文省略)
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
二 前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物
三 前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
三号建築物は、第一号、第二号の定義されている以外の建築物という書き方になっています。一号と二号以外の建築物という条件を読み解くと、平屋で200㎡以下となります。
既にご覧いただいた通り、建築基準法6条1項は第一号、第二号、第三号の3種類があります。この中でも『三号』だけは超超超特別なので、『三号建築物』というニックネームが付いているというイメージです。
どんな特別扱いがあるのか、続けて解説していきます。
Q.三号建築物と四号建築物の違いとは?

四号建築物っていうのも聞いたことがあるんだけど…どんな違いがあるの?
四号建築物は、死語です。(現在は、存在しない用語です)
令和7年4月1日の法改正より前は、四号建築物という用語が存在していました。四号建築物とは、木造の場合は2階以下500㎡以下、非木造の場合は平屋200㎡以下の建築物のことでした。
しかし、この規模が法改正によって縮小。その結果、現在の『構造を問わず、平屋で200㎡以下』と整理され、三号建築物と名称変更されたのです。

よって、現行の建築基準法では四号建築物は存在しません!だから、呼び分けるために、『旧四号建築物』と呼ぶケースもあるようです
三号建築物の『建築基準法の特別扱い』とは?
三号建築物の特別扱いとは、手続き規定が簡略化されること

よく勘違いされてしまうことだけど…あくまでも手続き規定(確認申請のなど)が緩和されるだけで、実態規定(構造耐力など)の緩和はないので、注意です!
よく、三号建築物だったら、構造耐力(法20条)は適用されない…などと勘違いされてしまいます。しかし、実際には三号建築物であっても、構造耐力(法20条)は、最低限仕様規定は適合させなくてはなりません。詳しい内容は、下記の記事を確認してみてください。

手続き規定の緩和って、具体的にどんな内容があるの?

具体的には、下記の5つの緩和があります!
三号建築物の緩和とは?
- 所定の条件を満たした場合確認申請が不要
- 確認申請の特例
- 検査の特例
- 建築物の使用制限の特例
- 省エネ適合性判定の有無

それぞれの内容を確認してみましょう!
確認申請が不要
三号建築物は、下記の場合、確認申請が不要となる
- 『都市計画区域、準都市計画区域、準計画区域、知事が定めた区域』以外に建築する場合
- 大規模な修繕、大規模な模様替
- 用途変更
確認申請とは、工事を着工する前に、建築基準法その他関係法令に適合しているのかどうか事前チェックを受けるものです。大事な制度ですが、確認申請が必要になると、手間や費用がかかってしまいます。確認申請については、下記の記事で詳しく解説しています。
原則として、『建築(新築・増築・改築・移転)』や『大規模修繕・大規模の模様替え』をする場合、確認申請は必要になります。

でも、三号建築物の場合には、所定の地域に建築物をする場合、大規模の修繕・模様替えをする場合などは確認申請が不要になるんです!
確認申請の特例
三号建築物には、確認申請で『審査される図書が少なくなる』という特例を受ける事が可能(建築士が設計したものに限る)
確認申請では、原則として、建築基準法のすべての内容を審査されることとなります。しかし、構造耐力(法20条)などの確認をすると、必要になる資料が多くなる、申請者にも大きな負担となります。

でも、三号建築物の場合、構造耐力(法20条)などの一部規定について、審査が省略されます!
詳しい内容については、下記の記事を確認してください。
ただし、あくまでも審査の省略ができるだけ。つまり、添付不要になったとしても設計者がしっかり建築基準法の適合は確認しなければならないので、注意してください。
検査の特例
検査も確認申請と同様に、三号建築物の特例を受ける事が可能(ただし、条件付き)
三号建築物は、確認申請の同様に検査の特例も受ける事ができます。どんな特例かというと、『特例で審査した内容だけを検査すればok』という特例です。
もし検査の特例を受けなかった場合、確認申請で特例を受けた部分も検査で全部確認をするという事になります。だから、検査の特例は基本的に受けるべきでしょう。

ただし、特例を受ける為には『特例写真の提出が必要』です。それは、規則4条1項二号の写真です。だから、うっかり写真を忘れると特例が受けられなくなる可能性があります。
検査の特例を受ける為の写真とは?
屋根の小屋組の工事終了時構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における
- 当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組の写真
- 仕口その他の接合部の写真
- 鉄筋部分等を写した写真

写真を忘れてしまうと、検査の特例が受けられなくなってしまうので、注意しましょう!
建築物の使用制限の特例
三号建築物は、検査済証の取得前であっても、建築物の使用が可能
原則として、検査済証を取得するまで、建築物を使用することはできません。しかし、三号建築物の場合は、検査済証の取得前であっても、建築物を使用することができます。
念の為、法文でも確認してみましょう。
建築基準法7条の6第1項
第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第十八条第三十八項及び第九十条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

本当だ!法第6条第1項第一号と第二号だけだから、三号建築物は含まれていないのね!

そうなんです!

じゃあ、私検査受けるのやめようかな!?建物使えるなら、全然いいし!

それは、建築基準法では認めませんよ!
なぜなら、建築基準法には『工事が完了してから4日以内の検査の申請をしなけれならない』という決まりがあるからです。(建築基準法7条1項、2項)だから、検査を受けずそのまま建築物を使う、というのは認められていないので、注意しましょう。
あくまで、一時的に使用するならOKというイメージです。

止むを得ず、検査前の建築物を使うとしても、検査を行う指定確認検査機関などに相談はしておきましょう!物などを運びすぎて、検査ができない状況になっていると大変ですからね…!
省エネ適合性判定の有無
三号建築物は、省エネ基準の適合が必要。ただし、省エネ適合性判定は不要(建築士が設計したものに限る)
こちらは、2025年4月で改正になった内容です。
三号建築物であっても、原則として、省エネ基準への適合が義務化されました。そして、基本的には省エネ適合性判定の取得をして、適合していることを第3者からのチェックが必要となります。
しかし、三号建築物の場合は、この省エネ適合性判定が不要となります。

省エネ基準に適合が必要だけど、審査はされないってことだね。なんか、似たような話を聞いたことがあるような…

そうですね!確認申請の特例の話と一緒です!
三号建築物は、確認申請の特例が使え、さらに、省エネ適合性判定も不要です。つまり、かなり申請が楽です。しかし、審査されないだけで、適合はさせなくてはならないので、注意が必要です。
建築法規の"判断ミス"を、未然に防ぎませんか?
登録特典の『建築法規「逆引き」判定シート』は、用途と規模を入力するだけで、適用条文を自動抽出。
現場で私が実際に使っている"逆引き思考"を、そのままシート化しました。
※登録後すぐにダウンロードできます
\ 登録特典:建築法規「逆引き」判断シート(Excel)/
まとめ:三号建築物は手続き関係で特別扱いされる
✔️三号建築物とは、平屋で200㎡以下の小規模な建築物のこと
✔️三号建築物は、下記の内容の特別扱いがある
- 都市計画区域等以外の確認申請の有無
- 確認申請の特例
- 検査の特例
- 建築物の使用制限の特例
- 省エネ適合性判定の有無
✔️しかし、特別扱いがあるので手続き規定のみで、実態規定は特別扱いがない。設計者がしっかりと確認することが重要